私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
コリント人への手紙第一(26)御霊の賜物(6)―正しい賜物の行使―14:26~40
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
正しい賜物の行使について学ぶ。
コリント人への手紙第一 26回
御霊の賜物(6)
―正しい賜物の行使―
14 :26~40
はじめに
1.文脈の確認
(1)御霊の賜物(12~14)
①御霊による信仰告白(12:1~3)
②一致と多様性(12:4~31)
③愛の優位性(13:1~13)
④異言よりも預言(14:1~25)
⑤正しい賜物の行使(14:26~40)
2.注目すべき点
(1)教会に混乱をもたらした最大の要因は、御霊の賜物の誤用であった。
(2)愛の章(13章)は、御霊の賜物の行使という文脈の中で出てくる。
(3)14章は、集会での賜物の行使に関する教えである。
(4)当時は、今のような礼拝形式がまだ確立していなかった。
3.アウトライン
(1)秩序の重要性(26~33節a)
(2)婦人の言動(33b~35節)
(3)最後の勧め(36~40節)
4.結論:異言の賜物に関する7つの教え
正しい賜物の行使について学ぶ。
Ⅰ.秩序の重要性(26~33節a)
1.26節
1Co 14:26
それでは、兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなたがたが集まるときには、それぞれが賛美したり、教えたり、啓示を告げたり、異言を話したり、解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを、成長に役立てるためにしなさい。
(1)26~28節は、異言の賜物の濫用を抑制するための教えである。
①異言の賜物が、礼拝に最も混乱をもたらしていた。
(2)当時の礼拝は、形式張らず、自由なものであった。
①聖霊が、御霊の賜物(複数の信者)を用いて自由に働かれた。
②初代教会の礼拝は、いわば「オープンミーティング」であった。
③各人が、自発的に礼拝の奉仕に参加していた。
(3)26節から垣間見える礼拝の様子
①ある人が賛美する(詩篇か)。
②別の人が、そこから着想を得た教えを語る。
③また別の人が、預言の賜物を発揮して啓示を語る。
④さらに異言で語る人と解き明かしをする人がことばを発する。
⑤賜物を行使する人たちは、愛(教会の霊的成長)をゴールとして奉仕をする。
2.27~28節
1Co 14:27
だれかが異言で語るのであれば、二人か、多くても三人で順番に行い、一人が解き明かしをしなさい。
1Co 14:28
解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対し、また神に対して語りなさい。
(1)異言の賜物の行使に関する教え
①礼拝で異言の賜物を用いる場合は、2人か3人に限定する。
②複数の人が同時に異言を語るのではなく、順番に行う。
③解き明かしができる者がいることが、異言を語るための条件である。
④解き明かす者がいなければ、教会の礼拝では黙っている。
⑤その人は、ことばに出さないで、自分と神に対して異言で語ればよい。
⑥全員が一斉に異言で祈ることは、許されていない。
3.29節
1Co 14:29
預言する者たちも、二人か三人が語り、ほかの者たちはそれを吟味しなさい。
(1)礼拝の中で預言する者を、2人か3人に限定する。
①異言を語る者の場合と同じである。
(2)ほかの者はそれを吟味する。
①神の霊によって語っているかどうかを見極める。
②もし神の霊によって語っていなければ、その人は偽預言者である。
4.30~31節
1Co 14:30
席に着いている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさい。
1Co 14:31
だれでも学び、だれでも励ましが受けられるように、だれでも一人ずつ預言することができるのです。
(1)別の人に啓示が与えられたなら、先に語っていた人は黙る。
①長く語っていると、人間的な判断が混入する危険性がある。
(2)預言者には一人ずつ順に預言する機会が与えられるべきである。
①その結果、だれでも学び、励ましを受けることができる。
5.32~33節a
1Co 14:32 預言する者たちの霊は預言する者たちに従います。
1Co 14:33a 神は混乱の神ではなく、平和の神なのです。
(1)コリントの信者たちの誤解
①聖霊に満たされている人ほど、自分を制御できないと考えていた。
②長く話し続けるのは、聖霊に満たされている証拠であると考えていた。
(2)パウロの教え
①預言の賜物を与える霊は、預言する者たちに従う。
②つまり、恍惚状態で預言するわけではない。
③預言者は、自分の意志で預言の賜物を制御することができる。
④神は混乱の神ではなく、平和の神である。
⑤混乱した礼拝の中には、神の臨在はない。
Ⅱ.婦人の言動(33b~35節)
1.33b~34
1Co 14:33b 聖徒たちのすべての教会で行われているように、
1Co 14:34
女の人は教会では黙っていなさい。彼女たちは語ることを許されていません。律法も言っているように、従いなさい。
(1)章と節は、後の時代に付加された。
①ここでは、33節の区分が不自然である。
②33節bは、本来34節に含まれるものである。
③これから教えることは、すべての教会に適用される普遍的真理である。
(2)婦人の役割
①婦人には多くの役割が与えられている。
*特に、家庭の管理、育児が重要である。
②しかし、教会の公の集会で発言することは、許されていない。
*これは、おしゃべりのことではない。
*権威をもって語ることである。
③「律法も言っているように」
*創3:16
Gen 3:16
女にはこう言われた。/「わたしは、あなたの苦しみとうめきを/大いに増す。/あなたは苦しんで子を産む。/また、あなたは夫を恋い慕うが、/彼はあなたを支配することになる。」
④「従いなさい」
*婦人の役割は、夫への従順である。
(3)明らかな矛盾をどのように解決するか。
①11:5
1Co 11:5
しかし、女はだれでも祈りや預言をするとき、頭にかぶり物を着けていなかったら、自分の頭を辱めることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。
②14:34
1Co 14:34 女の人は教会では黙っていなさい。彼女たちは語ることを許されていません。律法も言っているように、従いなさい。
③前者では、婦人が集会の中で祈りや預言をすることが許可されている。
③後者では、語られた預言に対して応答することが禁じられている。
*男に許されていることが婦人には許されていない。
④11:5と14:34は、矛盾ではない。
2.35節
1Co 14:35
もし何かを知りたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、女の人にとって恥ずかしいことなのです。
(1)質問すること自体が、教えることにつながる場合がある。
①そのような抜け穴を防ぐために、婦人には質問することが禁じられている。
②質問があれば、家で自分の夫に尋ねるべきである。
(2)未婚の女性や寡婦は、どうしたらよいのか。
①聖書は、一般原則を述べている。
②未婚の女性には、父や兄がいる。
③寡婦には、教会の長老がいる。
④神の秩序に違反するのは恥ずべきことである、という点を覚えておけばよい。
Ⅲ.最後の勧め(36~40節)
1.36節
1Co 14:36
神のことばは、あなたがたのところから出たのでしょうか。あるいは、あなたがたにだけ伝わったのでしょうか。
(1)パウロは、予想される反論に対して「皮肉」を用いて回答している。
①「使徒たちの教え」以上に、自分たちは深い知識を持っているというのか。
②神のことばは、あなたがたのところから出たというのか。
③あるいは、あなたがたにだけ伝わったというのか。
④神のことばは自分たちのところから出たと主張できる教会は、存在しない。
2.37~38節
1Co 14:37
だれかが自分を預言者、あるいは御霊の人と思っているなら、その人は、私があなたがたに書くことが主の命令であることを認めなさい。
1Co 14:38 それを無視する人がいるなら、その人は無視されます。
(1)パウロの教えは、彼自身が考えたことではない。
①それは、主の命令である。
②使徒たちの教えは、主ご自身から出たものである。
③自分を預言者や御霊の人と思っているなら、パウロの教えを認めるべきである。
(2)それを認めないなら、その人は預言者、御霊の人ではない。
①その人自身が、認められない状態にとどまることになる。
3.39節
1Co 14:39
ですから、私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。また、異言で語ることを禁じてはいけません。
(1)預言の賜物のほうが異言の賜物よりも優れている。
①預言のことばによって救いに導かれる未信者がいる。
②異言は、解き明かす人がいなければ、群全体の益にはならない。
③預言に関しては、それを熱心に求める。
④異言に関しては、それを禁じてはいけない。
4.40節
1Co 14:40 ただ、すべてのことを適切に、秩序正しく行いなさい。
(1)これが結論である。
①適切に、秩序正しく
②今も、すべての教会がこの命令に従っているわけではない。
結論:異言の賜物に関する7つの教え
1.異言を禁じてはならない(39節)。
2.公の集会で異言を語る場合は、解き明かす人がいなければならない(27~28節)。
3.公の集会で異言を語る人の人数は、最大3人までである(27節)。
4.異言を語る人は、同時にではなく、順番に語らなければならない(27節)。
5.異言の内容は、群の成長に役立つものでなければならない(26節)。
6.婦人は、語られた預言に応答することが許されていない(40節)。
7.すべての集会は、適切に、秩序正しく行うべきである(40節)。



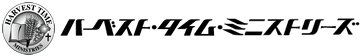
週間アクセスランキング
ヨハネの福音書(41)「新しい戒め」ヨハ13:31~38
ヨハネの福音書(40)「裏切りを予告するイエス」ヨハ13:21~30
60分でわかる新約聖書(21)ペテロの手紙第一
日本人のルーツはユダヤ人か(3)分子人類学から見た日ユ同祖論
60分でわかる旧約聖書(26)エゼキエル書
創世記(12)—洪水の背景—