私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(58)「復活」ヨハ20:1~18
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
イエスの復活は歴史的事実である。ペテロ、ヨハネ、マグダラのマリアの体験がそれを証明している。
ヨハネの福音書(58)
「復活」
ヨハ20:1~18
1.文脈の確認
(4)イエスの受難(18~20章)
①イエスの逮捕(18:1~11)
②イエスの宗教裁判(18:12~27)
③イエスの政治裁判(18:28~40)
④有罪判決(19:1~16)
⑤十字架刑(19:17~30)
⑥埋葬(19:31~42)
⑦復活(20:1~18)
2.注目すべき点
(1)「福音の三要素」は歴史的事実である(1コリ15:3~5)。
①キリストは、私たちの罪のために死なれた。
②また、葬られた。
③また、3日目によみがえられた。
(2)この箇所は、イエスの復活をめぐる最初の目撃証言である。
①空の墓は客観的証拠であり、主に出会うのは個人的経験である。
イエスの復活は歴史的事実である。
ペテロ、ヨハネ、マグダラのマリアの体験がそれを証明している。
Ⅰ.ペテロとヨハネの経験(1~11節)
1.1節
Joh 20:1
さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやって来て、墓から石が取りのけられているのを見た。
(1)「週の初めの日」は、イエスが復活した日、新しい創造の始まりの日である。
①マリアは早い時間に墓に行き、その後日の出とともに他の婦人たちと合流。
(2)神は、証人としての信頼性に欠ける女性を最初の復活の証人に選ばれた。
①復活の歴史的信頼性は、神の逆説的選びによって証明された。
(3)「墓から石が取りのけられていた」というのは、客観的事実である。
①このことは、単なる霊的体験や幻覚ではない。
2.2~3節
Joh 20:2
それで、走って、シモン・ペテロと、イエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。「だれかが墓から主を取って行きました。どこに主を置いたのか、私たちには分かりません。」
Joh 20:3 そこで、ペテロともう一人の弟子は外に出て、墓へ行った。
(1)マリアは、ペテロとヨハネに報告した。
①誰かが墓から死体を取って行った。
②「私たち」という複数形の主語を用いている。
*他の女たちは、自分たちが見聞きしたことを使徒たちに報告した。
③墓に走ったのは、マリアの話を聞いたペテロとヨハネだけだった。
*2人の証人の証言は信頼できる。
2.4~5節
Joh 20:4
二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。
Joh 20:5
そして、身をかがめると、亜麻布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。
(1)ヨハネの方が、足が速かった。
①年齢差か。伝承では、ヨハネが使徒たちの中で最も若かった。
(2)ヨハネは先に墓に着いたが、のぞき込んだだけで、中には入らなかった。
①亜麻布が置いてあるのを見た。
*この状況は、混乱ではなく、秩序を示唆している。
*「見た」けれど、まだ信仰には至っていない。
②中に入らなかったのは、儀式的汚れを恐れてのことであろう。
③あるいは、ペテロに先を譲ったか。
3.6~8節
Joh 20:6
彼に続いてシモン・ペテロも来て、墓に入り、亜麻布が置いてあるのを見た。
Joh 20:7
イエスの頭を包んでいた布は亜麻布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。
Joh 20:8
そのとき、先に墓に着いたもう一人の弟子も入って来た。そして見て、信じた。
(1)ペテロは到着すると、中に入って様子を確かめた。
①亜麻布は、イエスの死体をくるんだ状態のままで残されていた。
*頭に巻かれていた布切れは、離れた所に丸めてあった(たたんであった)。
②つまり、イエスのからだは亜麻布を通過してなくなっていた。
③これは、復活のからだが地上のからだとは異なることを示している。
④ラザロの場合は、亜麻布を解く必要があった。
(2)ヨハネはペテロに続いて墓に入った。
①ヨハネも同じものを見たが、その意味を理解した。
②彼は、イエスが復活したことを信じた(初歩的な信仰)。
③墓が開いたのは、弟子たちが中に入って確かめるためであった。
4.9~10節
Joh 20:9
彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書を、まだ理解していなかった。
Joh 20:10 それで、弟子たちは再び自分たちのところに帰って行った。
(1)これは、ヨハネの感想である。
①ペテロとヨハネは、「復活の預言」をまだ理解していなかった。
(2)墓に居続ける必要はないと判断し、彼らは町のどこかに戻って行った。
①体験はみことばの理解によって信仰と結びつく。
Ⅱ.マグダラのマリアの体験(11~18節)
1.11~12節
Joh 20:11
一方、マリアは墓の外にたたずんで泣いていた。そして、泣きながら、からだをかがめて墓の中をのぞき込んだ。
Joh 20:12
すると、白い衣を着た二人の御使いが、イエスのからだが置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。
(1)ペテロとヨハネが去っても、マグダラのマリアは墓に残った。
①愛する人を失くした喪失感がある。
②彼女にとっては、これは「通夜」(寝ずの番)である。
③主を慕い求める者に、特別な啓示が与えられた。
(2)彼女は、墓の中をのぞき込んだ。
①そこに二人の天使が、白い衣をまとって座っていた。
*二人の御使いの配置は、幕屋の贖いの座を意図的に想起させる。
②天使が現れる時は、通常、男性の姿を取る。
*例外的には、イザヤが見たセラフィムの幻がある(イザ6:1~13)。
③彼女には、超自然的なことが起こっているという認識がない。
④御使いの登場は、ユダヤ的背景では「神的承認のしるし」として理解される。
2.13~14節
Joh 20:13
彼らはマリアに言った。「女の方、なぜ泣いているのですか。」彼女は言った。「だれかが私の主を取って行きました。どこに主を置いたのか、私には分かりません。」
Joh 20:14
彼女はこう言ってから、うしろを振り向いた。そして、イエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。
(1)天使と対話しながら、マリアはそれに気づいていない。
①「女の方、なぜ泣いているのですか」
②「だれかが私の主を取って行きました」
*主に対する彼女の愛が溢れている。
③「どこに主を置いたのか、私には分かりません」
*人間の限界と悲しみが示されている。
(2)彼女はうしろを振り向いた。
①背後に人の気配を感じたのであろう。
②しかし、それがイエスであることが分からなかった。
③「認識できない状態」から「目が開かれる経験」への移行は典型的なパターン。
3.15節
Joh 20:15
イエスは彼女に言われた。「なぜ泣いているのですか。だれを捜しているのですか。」彼女は、彼が園の管理人だと思って言った。「あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。」
(1)イエスの質問
①「なぜ泣いているのですか。だれを捜しているのですか」
②マリアを真理へと導く優しい招きである。
(2)マリアの回答
①彼女は、その人を園の管理人(園丁、庭師)だと勘違いした。
②「あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。
私が引き取ります」
③なぜイエスだと認識できなかったのか。
*涙で目が曇っていた。
*イエスの姿があまりにも変化していた。
*神が一時的に霊的盲目状態を作り出された。
*喪失感が深くて、正常な判断ができなかった。
4.16~17節
Joh 20:16
イエスは彼女に言われた。「マリア。」彼女は振り向いて、ヘブル語で「ラボニ」、すなわち「先生」とイエスに言った。
Joh 20:17
イエスは彼女に言われた。「わたしにすがりついていてはいけません。わたしはまだ父のもとに上っていないのです。わたしの兄弟たちのところに行って、『わたしは、わたしの父であり、あなたがたの父である方、わたしの神であり、あなたがたの神である方のもとに上る』と伝えなさい。」
(1)マリアにイエスであるとの認識が生まれた。
①旧約聖書で最大の「認識事件」は「私はヨセフです」である(創45:1~3)。
②歴史上最大の「認識事件」はイエスを園丁と思ったことである。
③イエスを認識するきっかけは、「マリア」という呼びかけである。
④善き羊飼いは羊の名を呼び、羊はそれについて行く(ヨハ10:3、4)。
⑤終末時代に、ユダヤ人はイエスがメシアであることを認識する(ゼカ12:10)。
(2)彼女は振り向いた。
①ヘブル語で、「ラボニ」と言った。敬愛と親しみを込めた呼びかけ。
②「私の先生」というニュアンスが含まれている。
(3)イエスは、マリアがイエスに触れることを許さなかった。
①「わたしはまだ父のもとに上っていないのです」がその理由であった。
②贖罪の日の大祭司の奉仕に対応している。
③イエスはこの後、ご自身の血を携えて天の至聖所に入り、幕屋を清められた。
④信者は今「大祭司キリスト」を通して御座に近づける(ヘブ4:14~16)。
(4)マリアへの命令
①「わたしの兄弟たちのところに行って」
*イエスを信じる者たちは、神を天の父とする家族である。
*ロマ8:29
②「わたしは、わたしの父であり、あなたがたの父である方、わたしの神であり、
あなたがたの神である方のもとに上る」
*イエスは神の家族の中の長子である。
*しかし、イエスと神の関係は、私たちと神の関係とは違う。
*イエスの場合は、「わたしの父」である。
*私たちの場合は、「私たちの父」である。
(5)マリアには、新しい使命が与えられた。復活の証人としての使命である。
①天使たちを見た。
②復活のイエスを見た。
③最初の目撃者となった。
④よき知らせを伝える者となった。
5.18節
Joh 20:18
マグダラのマリアは行って、弟子たちに「私は主を見ました」と言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。
(1)マグダラのマリアは、弟子たちによき知らせを伝えた。
①彼女は「使徒たちへの使徒」となったのである。
*「私は主を見ました」は、理解をともなった確信的な目撃である。
②しかし弟子たちは、彼女の証言を信じなかった(他の女たちの証言も)。
今日の信者への適用
1.復活は歴史的事実である。
(1)信仰は事実に基づく。
(2)マリアが最初に見たのは「石が取りのけられた墓」だった。
(3)ペテロとヨハネも布が整然と置かれているのを確認した。
(4)感情ではなく、十字架と復活という確かな出来事を信仰の土台とすべき。
2.復活は悲しむ者への慰めである。
(1)マリアは墓の前で泣き続けた。
(2)しかし、主は彼女に優しく語りかけられた。
(3)涙のただ中に主は立っておられる。
(4)主は、個人的に呼ばれるお方である。
3.復活は新しい関係と使命の始まりである。
(1)マリアは、復活の証人として遣わされた。
(2)「わたしの父、あなたがたの父」
(3)復活は信者を神の家族に迎え入れる新しい関係を確立した。



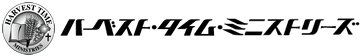
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(11)―24章でたどる神の救済史 10章 「新しい契約」エレミヤ書31章
創造から新天新地へ(10)―24章でたどる神の救済史 9章 「受難のしもべの預言」イザヤ書53章
創造から新天新地へ(09)―24章でたどる神の救済史 8章 「王国崩壊の理由」列王記第二25章
創造から新天新地へ(08)―24章でたどる神の救済史 7章 「ダビデ契約とメシアの希望」サムエル記第二7章
創造から新天新地へ(07)―24章でたどる神の救済史 6章 「奴隷生活から定住生活へ」ヨシュア記1章
創造から新天新地へ(05)―24章でたどる神の救済史 4章 「イスラエル民族の始まり」出エジプト記12章