私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(56)「十字架刑」ヨハ19:17~30
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
イエスは3つの役割を果たされた。イエスは王であり、大祭司であり、贖い主である。
関連キーワード
ヨハネの福音書(56)
「十字架刑」
ヨハ19:17~30
1.文脈の確認
(4)イエスの受難(18~20章)
①イエスの逮捕(18:1~11)
②イエスの宗教裁判(18:12~27)
③イエスの政治裁判(18:28~40)
④有罪判決(19:1~16)
⑤十字架刑(19:17~30)
2.注目すべき点
(1)王としてのイエスの姿が描かれる。
(2)大祭司としてのイエスの姿が描かれる。
(3)贖い主としてのイエスの姿が描かれる。
イエスは3つの役割を果たされた。
イエスは王であり、大祭司であり、贖い主である。
Ⅰ.王としてのイエスの姿(17~22節)
1.17節
Joh 19:17イエスは自分で十字架を負って、「どくろの場所」と呼ばれるところに出て行かれた。そこは、ヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。
(1)イエスは自分で十字架を負った。
①共観福音書では、クレネ人シモンが途中から十字架を担がされた。
②ヨハネの強調点は、イエスが主体的に贖いの道を歩まれたことにある。
③十字架の死は、自ら進んで選ばれたものである。
(2)「どくろの場所」と呼ばれるところに出て行った。
①ヘブル語でゴルゴタ、ラテン語でカルバリ
②ユダヤの伝承では、アダムの頭蓋骨が埋葬された場所だとされる。
③ゴルゴタでの死は、旧約のいけにえ制度の型の完成である。
④「宿営の外で焼かれる」贖罪のいけにえ(レビ16:27)の成就。
2.18節
Joh 19:18
彼らはその場所でイエスを十字架につけた。また、イエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に、ほかの二人の者を一緒に十字架につけた。
(1)イエスを真ん中にした。
①「罪人とともに数えられた」(イザ53:2)
②人類を二分する象徴
*イエスをどう受け入れるかが唯一の分岐点になる。
③人間的には辱めの象徴、霊的には「王として中央に座する」姿。
*これはヨハネの神学(十字架=栄光の顕現)に即している。
④ヨハネの福音書全体でイエスは「中心に立つお方」(7:37、8:2、20:19)。
⑤イエスは贖いの歴史の中心に立ち、全人類の行く末を決定する中心人物。
3.19~20節
Joh 19:19
ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」と書かれていた。
Joh 19:20
イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。
(1)罪状書き
①罪状を記した札が犯人の首に掛けられた。
②後に十字架の上に掲げられた。
(2)「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」と書かれていた。
①「自称ユダヤ人の王ナザレのイエス」を皮肉に強調した表現
②神の視点からは、これは真理の宣言である。
③人間の意図を越えて、神の計画が成就している例である。
(3)3言語で書かれたことの意味
①ヘブル語:ユダヤ人の宗教的言語。
②ラテン語:ローマ帝国の公用語、政治と権力の象徴。
③ギリシア語:国際共通語、文化と哲学の象徴。
(4)イエスが全世界の王であることの象徴。
①すべての民族・文化・言語に対する普遍的支配を示す(黙7:9)。
②「多くのユダヤ人が読んだ」(20節)。群衆への公的証言。
③十字架は敗北の場ではなく、真の王が即位する場である。
④ヨハネ独特の「逆説的栄光の神学」。
4.21~22節
Joh 19:21
そこで、ユダヤ人の祭司長たちはピラトに、「ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてください」と言った。
Joh 19:22 ピラトは答えた。「私が書いたものは、書いたままにしておけ。」
(1)ユダヤ人の指導者たちの抗議
①群衆に誤解を与えないために「自称した」と書くように求めた。
(2)ピラトの回答
①「私が書いたものは、私が書いたのだ」
②皮肉と反抗のことば。ユダヤ人に対する最後の抵抗。
③「イエスがユダヤ人の王である」ことを確定する宣言となった。
④黙19章では「王の王、主の主」として再臨される。先取りの宣言。
Ⅱ.大祭司としてのイエス(23~27節)
1.23節
Joh 19:23
さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに織った、縫い目のないものであった。
(1)ローマ兵の行為
①処刑にあたった兵士たちは、受刑者の衣服を分け合う慣習があった。
②イエスの衣服は5点あったと考えられる。
*外套、ベルト、サンダル、ターバン(または頭巾)、下着
③兵士は4人(小隊の一班)。4点を分け、残る「下着」が問題となった。
(2)縫い目のない下着
①ヨハネは特に「縫い目のない一枚織りの下着」であったことを強調する。
②現代の下着(肌着)とは違い、長袖または半袖のワンピース型の衣服。
③材質は麻布や羊毛で、縫い目のない「無縫製のチュニック」も存在。
④出エジ28:31~32:大祭司の服は「一枚織り」で作られた。
⑤イエスの衣服は 「真の大祭司」としての象徴と解釈できる。
(3)神学的意味
①人間の目には「敗北した罪人」と映るが、その衣服は大祭司であることを示す。
②イエスは十字架上で「大祭司」としての働きを成就している。
③いけにえの動物ではなく、ご自身を献げている。
2.24節
Joh 19:24
そのため、彼らは互いに言った。「これは裂かないで、だれの物になるか、くじを引こう。」これは、/「彼らは私の衣服を分け合い、/私の衣をくじ引きにします」/とある聖書が成就するためであった。それで、兵士たちはそのように行った。
(1)兵士たちの行為
①下着(キトン)は裂くと価値が下がるため、くじを引いて所有者を決めた。
②人間的には単なる習慣・偶然の行為、神の視点では預言の成就。
(2)詩22:18の成就
Psa 22:18 彼らは私の衣服を分け合い/私の衣をくじ引きにします。
①ダビデの詩の中に描かれた受難の姿が、逐語的に実現した。
②兵士の無意識の行為さえ、神の主権のもとで預言成就の一部となる。
(3)大祭司としての完成(ヘブ4:16)
①衣を裂かれずに残したことは、大祭司の衣の完全性を保つ象徴でもある。
②大祭司は衣を裂いてはならない(レビ21:10)。
3.25節
Joh 19:25
イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。
(1)女性の信仰の忠実さ
①他の弟子たちが逃げる中、女性たちは信仰と愛のゆえに最後まで残った。
②神は「弱いと思われる者」を用いて、最も重要な証人とされた。
(2)マリアの立場
①母マリアの苦しみは特別である。
②彼女は「救い主の母」であって「救い主」ではない。
③ヨハネは、マリアを「苦しむ一人の信仰者」として描いている。
(3)十字架のそばにいる人々は、後に教会を形作る信仰共同体の雛形。
①ユダヤ人女性たちが中心にいる。教会がユダヤ的背景を持つことを示唆。
4.26~27節
Joh 19:26
イエスは、母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に「女の方、ご覧なさい。あなたの息子です」と言われた。
Joh 19:27
それから、その弟子に「ご覧なさい。あなたの母です」と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分のところに引き取った。
(1)新しい共同体形成
①母を弟子ヨハネに託すことで、信仰による新しい家族共同体を指し示した。
②これは教会時代における「神の家族」の先取り。
③イエスとマリアの母子関係は断ち切られ、主従関係が始まった。
(2)マリアの位置づけ
①マリアは「救い主の母」ではあるが、救いにおいてはあくまで「一信仰者」。
②イエスが「女の方」と呼んだのは、マリア崇拝を否定する聖書的根拠である。
(3)なぜ弟子ヨハネに委ねられたのか。
①この時点でイエスの肉の兄弟たちは不信仰だった。
②ゆえに「信仰に基づく関係」が優先された。
Ⅲ.贖い主としてのイエス(28~30節)
1.28~29節
Joh 19:28
それから、イエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、「わたしは渇く」と言われた。
Joh 19:29
酸いぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは、酸いぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝に付けて、イエスの口もとに差し出した。
(1)「わたしは渇く」は詩篇69:21の直接的成就。
①イエスのことばは単なる苦痛の叫びではなく、預言成就の宣言。
(2)肉体と霊の両面の渇き
①イエスは真の人間として肉体的渇きを経験された。
②同時に、神からの断絶の中で霊的な渇きを経験された。
③これによって、私たちが「永遠に渇かない」救いを得る(4章、7章)。
(3)贖いの完成への布石
①このことばは「完了した」(19:30)の直前に置かれている。
②イエスは預言成就を最後まで意識し、計画的に贖いを完成させた。
2.30節
Joh 19:30
イエスは酸いぶどう酒を受けると、「完了した」と言われた。そして、頭を垂れて霊をお渡しになった。
(1)「テテレスタイ」の法的意味
①「完全に支払い済み」という法的・商取引的用語。
②人類の罪の借金が完全に支払われ、追加の償いは不要となった。
(2)旧約制度の終結と完成
①動物の犠牲・律法・祭司制度はすべてここで完成。
②イエスは「大祭司」として、ご自身を唯一無二のいけにえとして献げた。
(3)主体的死
①「霊を渡された」は、イエスが自発的に死を選び取られたことを示す。
②十字架の死は強制ではなく、愛による自由意志のささげ物。
結論:今日の信者への適用
1.十字架が人類を二分する事実を受け止める。
(1)十字架は今も、人を「信じる者」と「拒む者」に分けている。
(2)この分岐点の現実を覚え、十字架を伝える使命を担う必要がある。
2.王なるイエスを告白する。
(1)「ユダヤ人の王ナザレのイエス」との札は3言語で掲げられた。
(2)ここには終末の出来事の先取りがある。
(3)イエスを王と告白するとは、日常生活のすべての領域に主権を認めること。
3.教会は新しい家族であることを認識する。
(1)イエスは母と愛する弟子を新しい家族として結びつけた。
(2)血縁よりも深い「霊的家族」として教会を理解すべきである。
(3)互いに重荷を担い合うべきである(ガラ6:2)。
(4)かしらであるキリストに近づくほどに、霊的家族の実体が完成する。
4.贖いの完成に立って生きる。
(1)「完了した」は罪の支払いが完全に終わったという宣言。
(2)救いの不確かさや「わざによる贖い」に縛られる必要がない。
(3)完成した救いに立ち、安心と確信の中で生きるべきである。



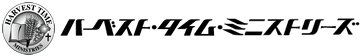
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(11)―24章でたどる神の救済史 10章 「新しい契約」エレミヤ書31章
創造から新天新地へ(10)―24章でたどる神の救済史 9章 「受難のしもべの預言」イザヤ書53章
創造から新天新地へ(09)―24章でたどる神の救済史 8章 「王国崩壊の理由」列王記第二25章
創造から新天新地へ(08)―24章でたどる神の救済史 7章 「ダビデ契約とメシアの希望」サムエル記第二7章
創造から新天新地へ(07)―24章でたどる神の救済史 6章 「奴隷生活から定住生活へ」ヨシュア記1章
創造から新天新地へ(05)―24章でたどる神の救済史 4章 「イスラエル民族の始まり」出エジプト記12章