私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(22)姦淫の場で捕えられた女ヨハ7:53~8:11
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
姦淫の女の物語から教訓を学ぶ。
ヨハネの福音書(22)
姦淫の場で捕えられた女
ヨハ7:53~8:11
1.文脈の確認
(1)前書き(1:1~18)
(2)イエスの公生涯(1:19~12:50)
①公生涯への序曲(1:19~51)
②初期ガリラヤ伝道(2:1~12)
③最初のエルサレム訪問(2:13~3:36)
④サマリア伝道(4:1~42)
⑤ガリラヤ伝道の再開(4:43~54)
⑥2度目のエルサレム訪問(5:1~47)
⑦後期ガリラヤ伝道(6:1~7:9)
⑧3度目のエルサレム訪問(7:10~10:42)
*仮庵の祭りでの教え(7:10~44)
*指導者たちの不信仰(7:45~52)
*姦淫の場で捕えられた女(7:53~8:11)
2.注目すべき点
(1)初期の写本群には、この箇所は含まれていない。
(2)福音派は、ヨハネの福音書の原典の一部ではないと考える。
(3)カトリックは、ブルガタ訳に入っているので、聖典の一部と認める。
(4)ヨハ20:30
Joh 20:30 イエスは弟子たちの前で、ほかにも多くのしるしを行われたが、それらはこの書には書かれていない。
(5)信頼できる初期の伝承が、写本を書く書記によって付加されたのであろう。
(6)ほとんどの学者が、これを歴史的事実と認める。
3.アウトライン
(1)状況説明(7:53~8:2)
(2)指導者たちの罠(3~6節a)
(3)イエスの応答(6b~8節)
(4)結末(9~12節)
4.結論:私たちへの適用
姦淫の女の物語から教訓を学ぶ。
Ⅰ.状況説明(53~2節)
1.53~1節
Joh 7:53 〔人々はそれぞれ家に帰って行った。
Joh 8:1 イエスはオリーブ山に行かれた。
(1)祭りが終わったので、人々はそれぞれの家に帰った。
①イエスを顔と顔を合わせて見て、信じる人たちが起こされた。
②しかし、大半の人たちがイエスを拒否した。
③指導者たちは、早くイエスを逮捕せねばならないと確信した。
(2)1節の冒頭にあるギリシア語の「de」が訳されていない。
①訳せば「しかし」(but)である。
②イエスには、枕するところもないのである。
③ベタニヤに宿泊することもあったが、オリーブ山が主な宿泊地であった。
2.2節
Joh 8:2
そして朝早く、イエスは再び宮に入られた。人々はみな、みもとに寄って来た。イエスは腰を下ろして、彼らに教え始められた。
(1)朝早く、イエスは再び宮に入られた。
①オリーブ山からキデロンの谷に下り、そこから神殿に上る。
②徒歩で30分弱の移動である。
(2)ルカ21:37~38
Luk 21:37 こうしてイエスは、昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。
Luk 21:38 人々はみな朝早く、教えを聞こうとして、宮におられるイエスのもとにやって来た。
①民衆は、いつものパターンに従って行動している。
②指導者たちは、イエスが神殿のどこで教えるかを予想できた。
Ⅱ.指導者たちの罠(3~6節a)
1.3~5節
Joh 8:3
すると、律法学者とパリサイ人が、姦淫の場で捕らえられた女を連れて来て、真ん中に立たせ、
Joh 8:4 イエスに言った。「先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。
Joh 8:5
モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。」
(1)律法学者とパリサイ人が、イエスのもとに来た。
①律法学者は、律法の研究をし、写本を制作する法律の専門家である。
②パリサイ人は、パリサイ派に属する人である。
③彼らは複数の証人によって、ある女の罪を糾弾しようとしている。
④「先生」という呼びかけは偽善である。
(2)姦淫の場で捕えられたひとりの女が真ん中に置かれた。
①恐らく既婚の女性であろう。姦淫(モイケイア)と淫行(ポルネイア)
②証人が複数いる。
③誰が見ても有罪が宣言されるケースである。
④申19:15
Deu 19:15
いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。
(3)姦淫に関するモーセの律法の規定
①レビ20:10
Lev 20:10 人が他人の妻と姦淫したなら、すなわち自分の隣人の妻と姦淫したなら、その姦淫した男も女も必ず殺されなければならない。
②申22:22
Deu 22:22
夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうして、あなたはイスラエルの中からその悪い者を除き去りなさい。
(4)モーセの律法によれば、男女ともに裁かれなければならない。
①ここでは、相手の男の姿がない。
②これは仕組まれた罠である。
③指導者たちが訴えている方法自体が、すでに律法違反である。
(5)律法学者とパリサイ人は、イエスに挑戦した。
①モーセの律法によれば、この罪は石打ちに当たる。
②「あなた」に強調がある。
③イエスが、モーセの律法をどう解釈し、どう適用するかを問うたのである。
2.6節a
Joh 8:6a
彼らはイエスを告発する理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。
(1)彼らは、イエスを告発する理由を得ようとした。
①告発する理由が見当たらないので、自分たちでそれを作り出した。
②これまで口伝律法を巡る議論が行われてきたが、成功しなかった。
③そこで、モーセの律法を取り上げている。
(2)イエスはジレンマに直面した(正義と恵みをいかに調和させるか)。
①石打ちの刑を命じた場合の結果
*その可能性は、大いにある。
*恵みに溢れた寛大なメシアだという評価と矛盾する。
*指導者たちは、イエスをローマの法廷に引き渡すことができる。
*ヨハ18:31
Joh 18:31
そこで、ピラトは言った。「おまえたちがこの人を引き取り、自分たちの律法にしたがってさばくがよい。」ユダヤ人たちは言った。「私たちはだれも死刑にすることが許されていません。」
②罪の赦しを宣言した場合の結果
*モーセの律法に反する宣言をしたことになる。
*それゆえ、イエスはメシアではないと判断される。
Ⅲ.イエスの応答(6b~8節)
1.6節b
Joh 8:6b だが、イエスは身をかがめて、指で地面に何か書いておられた。
(1)イエスは地面に何を書かれたのか。
①動詞はカタグラフォである。
*文字でも、絵でも、何かのしるしでも、すべて可能性あり。
②ある人たちは、イエスが告発する人たちの罪を書いていたと推測する。
③イエスが書いたものは残っていないが、文字を書けたことは確かである。
(2)強調点は「指で」にある。
①何を書いていたかは、重要ではない。
②モーセの律法は613の規定から成っている。
③十戒だけが、神の手によって書かれた。
④姦淫の禁止は、十戒の中に出てくる。
(3)旧約聖書の証言
①出31:18
Exo 31:18 こうして主は、シナイ山でモーセと語り終えたとき、さとしの板を二枚、すなわち神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになった。
②出32:15~16
Exo 32:15 モーセは向きを変え、山から下りた。彼の手には二枚のさとしの板があった。板は両面に、すなわち表と裏に書かれていた。
Exo 32:16 その板は神の作であった。その筆跡は神の筆跡で、その板に刻まれていた。
(4)イエスは、モーセの律法の作者である。
①告発する者たちは、罪を正すための正当な手続きを踏んでいない。
②イエスは、彼らの動機が間違っていることを知っておられた。
③イエスは、時間を置くことで彼らに悔い改めの機会を提供しておられた。
2.7~8節
Joh 8:7
しかし、彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。」
Joh 8:8 そしてイエスは、再び身をかがめて、地面に何かを書き続けられた。
(1)イエスのことばの背景には、モーセの律法のラビ的解釈がある。
①申17:6~7
Deu 17:6 二人の証人または三人の証人の証言によって、死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑に処してはならない。
Deu 17:7 死刑に処するには、まず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうして、あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。
②最初に石を投げる証人は、同じ罪を犯していない人でなければならない。
*無罪という意味ではない。
③イエスは、証人たちが同じ罪を心に宿していることを知っていた。
*イエスは、姦淫の女ではなく、指導者たちを裁かれた。
(2)イエスは、罪の裁きを否定しているわけではない。
①イエスは、モーセの律法の正しい運用を命じられた。
②イエスは、罪を大目に見ているのではなく、指導者たちの罪を糾弾された。
③指導者たちは、ジレンマに直面させられた。
(3)イエスは、再び身をかがめて、地面に何かを書き続けられた。
①指導者たちに、自らを省みる時間を与えた。
Ⅳ.結末(9~12節)
1.9節
Joh 8:9
彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去って行き、真ん中にいた女とともに、イエスだけが残された。
(1)証人たちは、全員が去って行った。
①年長者は先に良心の呵責を覚えたのであろう。
②彼らは、同じ罪を心に宿していたのである。
③告発する者と証人がいなくなったので、告発は無効になった。
(2)イエスと女だけがその場に残された。
①人の罪を裁くことができるのは、イエスだけである。
②群衆もいたであろう。
2.10~11節
Joh 8:10
イエスは身を起こして、彼女に言われた。「女の人よ、彼らはどこにいますか。だれもあなたにさばきを下さなかったのですか。」
Joh 8:11
彼女は言った。「はい、主よ。だれも。」イエスは言われた。「わたしもあなたにさばきを下さない。行きなさい。これからは、決して罪を犯してはなりません。」〕
(1)イエスは、女に敬意を示した。
①イエスは、女の罪よりも彼女を訴える者たちに関心を示された。
②訴える者たちがいなくなったので、告発は無効となった。
③彼女は、やがて裁き主キリストの前に立つが、今ではない。
④彼女にやり直しの機会が与えられた。
⑤イエスは、女の罪を大目に見たのではない。
⑥イエスは、神の小羊として罪の贖いの代価を支払おうとしておられる。
(2)律法学者とパリサイ人は、謙遜にさせられた。
①これ以降、イエスに罠を仕かけることはなくなった。
結論:私たちへの適用
1.律法と恵みは、神の愛の両輪である。
(1)律法の役割は、私たちの罪を示すことである。
(2)罪を認識した者の罪を赦すのが、恵みである。
2.赦されない罪はない。
(1)罪の赦しの根拠は、イエスの十字架の死である。
(2)赦しを受け取る方法は、信仰である。
3.他人を裁く前に、自分も同じ罪を犯していないかどうか、吟味すべきである。
(1)神から与えられている時間を有効に用いる。
(2)自分の罪を示されたなら、それを告白して、清めを受ける。
4.赦しは、罪を犯し続けることへの許可証ではない。
(1)赦しは、立ち直りへの招待状である。
(2)神の裁きは延期されたが、やがて神の裁きの前に立つ日がやってくる。



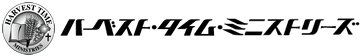
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(13)―24章でたどる神の救済史 12章 「帰還の命令」歴代誌第二36章
創造から新天新地へ(14)―24章でたどる神の救済史 13章 「約束の系譜に現れた救い主」マタイの福音書1章
創造から新天新地へ(12)―24章でたどる神の救済史 11章 「終末の王国」ダニエル書7章
使徒の働き(89)―ペリクスの前に立つパウロ―
日本人のルーツはユダヤ人か(3)分子人類学から見た日ユ同祖論
60分でわかる旧約聖書(27)ダニエル書