私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(53)「イエスの宗教裁判」ヨハ18:12~27
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
イエスは主権者である。このことは4つの段階を通して明らかになる。
ヨハネの福音書(53)
「イエスの宗教裁判」
ヨハ18:12~27
1.文脈の確認
(1)前書き(1:1~18)
(2)イエスの公生涯(1:19~12:50)
(3)イエスの私的奉仕(13:1~17:26)
(4)イエスの受難(18~20章)
①イエスの逮捕(18:1~11)
②イエスの宗教裁判(18:12~27)
2.注目すべき点
(1)イエスは抵抗せず、自ら進んで捕らえられた。
①主権者はイエスである。
(2)イエスはアンナスのもとへ連行された。
①公的な大祭司はカヤパであった。
②アンナスは「影の権力者」であった。
(3)光と闇の対比が描かれている。
①イエスは真理を公然と語る「光の側」。
②ペテロは火のそばで闇に取り込まれていく「弱さの側」。
イエスは主権者である。
このことは4つの段階を通して明らかになる。
Ⅰ.アンナスのもとに連行されるイエス(12~14節)
1.12~13節
Joh 18:12 一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちは、イエスを捕らえて縛り、
Joh 18:13 まずアンナスのところに連れて行った。彼が、その年の大祭司であったカヤパのしゅうとだったからである。
(1)イエスは抵抗しなかった(神の主権)。
①ローマ権力とユダヤ宗教権威が結託した異常事態。
②無抵抗のイエスを不必要に縛ったのは、恐れと敵意の反映である。
(2)「まず」(プロウトン)は強調で、裁判の順序の異常さを示す。
①現職の大祭司カヤパのもとへ行くべきだが、アンナスに送られた。
②これは権力構造の実体を暴露している。
③アンナスはカヤパの義父であった。
(3)アンナスが築いた「祭司の王朝」
①アンナスは紀元6~15年にローマから任命された大祭司。
②その後、5人の息子と娘婿カヤパが大祭司職についた。
③事実上「祭司の王朝」を築き、宗教権力の背後に君臨。
④ユダヤ人の間では、実質的権威はアンナスにあると見られていた。
2.14節
Joh 18:14 カヤパは、一人の人が民に代わって死ぬほうが得策である、とユダヤ人に助言した人である。
(1)カヤパは紀元18–36年の大祭司。
①ローマによって任命され、政治的にローマの意向に沿う立場にあった。
② 彼の発言を繰り返している(ヨハ11:50)。
③「ローマの怒りを避けるためにイエスを犠牲にしよう」という政治的助言。
④ヨハネは、それを「神の救済計画の預言」と読み直している。
Ⅱ.イエスを拒むペテロ(15~18節)
1.15~16節
Joh 18:15 シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、
Joh 18:16 ペテロは外で門のところに立っていた。それで、大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出て来て、門番の女に話し、ペテロを中に入れた。
(1)従う者の違い
①動揺するペテロ
②静かな証人ヨハネ
(2)社会的立場の違いを用いる神
①「もう一人の弟子」とはヨハネである。
②彼は大祭司の知り合いであった。
③彼の身分が用いられた結果、裁判記録が残されることになった。
(3)外に立つ危うさ
①中途半端な立ち位置が否認を招く。
2.17~18節
Joh 18:17 すると、門番をしていた召使いの女がペテロに、「あなたも、あの人の弟子ではないでしょうね」と言った。ペテロは「違う」と言った。
Joh 18:18 しもべたちや下役たちは、寒かったので炭火を起こし、立って暖まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って暖まっていた。
(1)「あなたも、あの人の弟子ではないでしょうね」
①μὴ + 疑問形 → 「否定を予想する質問」
②「まさか、あんたもこの人の弟子じゃないよね?」
③ペテロにとっては答えやすい状況(しかし信仰的には試練)。
(2)「違う」
①短い断言
②ペテロの明確な否認。ここで第1回目の否認が成立。
③「召使いの女」の前での否認は、人間の弱さを露わにしている。
(3)「炭火」
①春先、夜間は冷える。
②ペテロは敵の陣営の中に立っている。
③ヨハネ21:9(ペテロの回復の場面)でも再登場。
④意図的な対比:「否認の炭火」と「回復の炭火」。
Ⅲ.イエスを尋問するアンナス(19~24節)
1.19節
Joh 18:19 大祭司はイエスに、弟子たちのことや教えについて尋問した。
(1)アンナスは「大祭司」と呼ばれている。
①実質的な権威を有していた。
②大祭司は終身職なので、辞職後もそう呼ばれる資格があった。
(2)尋問の内容
①弟子たちのこと
*仲間の規模や性質に関心を持っていた。
*反乱分子がどうかを探る政治的意図を反映している。
②教え
*イエスの教えが律法に違反していないかを追求する意図がある。
(3)アンナスによる「予備審問」は違法である。
①証人を呼ばず、イエス本人に直接尋問している。
2.20~21節
Joh 18:20 イエスは彼に答えられた。「わたしは世に対して公然と話しました。いつでも、ユダヤ人がみな集まる会堂や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。
Joh 18:21 なぜ、わたしに尋ねるのですか。わたしが人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら、わたしが話したことを知っています。」
(1)「世に対して公然と話した」
①大胆に、率直に、公然と
②完了形(λελάληκα)で「今もその影響が残っている」ことを強調。
③イエスの宣教は秘密結社ではなく、誰でも聞くことができた。
(2)「何も隠れて話してはいません」
①同じ事実を別の角度から述べている。
②宣教が公のものであることは、今も変わっていない。
(3)「なぜ、わたしに尋ねるのか」
①反問形で、アンナスの取り調べが不当であることを指摘。
②ユダヤ法では、裁判は必ず証人によって立証されるべき。
(4)「それを聞いた人たちに尋ねよ」
①完了形「ἀκηκοότας」で、「聞いたことがあり、今も覚えている者たち」。
②つまり、証人を呼べばすぐに確認できるという意味。
③裁判の不当性を指摘された。
3.22~23節
Joh 18:22 イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が、「大祭司にそのような答え方をするのか」と言って、平手でイエスを打った。
Joh 18:23 イエスは彼に答えられた。「わたしの言ったことが悪いのなら、悪いという証拠を示しなさい。正しいのなら、なぜ、わたしを打つのですか。」
(1)「平手でイエスを打った」
①侮辱行為の意味が強い。
②公判中の被告を殴ることはユダヤ法でも違法。
(2)下役の行為は、不正を覆い隠すための暴力である。
①十字架の道への第一歩
(3)イエスは、冷静に裁判の正当性を求めた。
①侮辱を受けつつも、依然として「裁く者」としての姿を示す。
4.24節
Joh 18:24 アンナスは、イエスを縛ったまま大祭司カヤパのところに送った。
(1)イエスは「縛られたまま送られた」
①アンナスが実質権力を握りながらも公式裁判権はなく、カヤパに移送された。
②不正な尋問と屈辱の継続
③それは、神の救済計画の一部であった。
Ⅳ.イエスを3度拒むペテロ(25~27節)
1.25節
Joh 18:25 さて、シモン・ペテロは立ったまま暖まっていた。すると、人々は彼に「あなたもあの人の弟子ではないだろうね」と言った。ペテロは否定して、「弟子ではない」と言った。
(1)ペテロはすでに1度否認した後も、「敵陣」にとどまっていた。
①からだは温まったが、心は冷えていた。
(2)今度は「人々」が質問した。圧力が増している。
①否定を予想する質問である。
②ペテロは、短く答えた。
2.26~27節
Joh 18:26 大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。「あなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが。」
Joh 18:27 ペテロは再び否定した。すると、すぐに鶏が鳴いた。
(1)肯定的答えを期待する質問
①3度目で「完全な否認」に到達した。
②他の福音書によると、ペテロは「呪いをかけて誓って」否認した(マタ26:74)。
(2)否認の進展
①1回目(17節):召使いの女 → 軽い問いかけ。
②2回目(25節):複数の人々 → 社会的圧力が増す。
③3回目(27節):大祭司のしもべ → 証拠を伴う問いかけ。
(3)ヨハ13:38の成就
Joh 13:38 イエスは答えられた。「わたしのためにいのちも捨てるのですか。まことに、まことに、あなたに言います。鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと言います。」
①ペテロの失敗は、神の計画の中で許容されていた。
②ペテロの回復が用意されていた(ヨハ21章)。
結論:今日の信者への適用
1.人間の権威と神の主権
(1)イエスは下役に「縛られ」たが、実際にはご自身を進んで差し出しておられた。(2)環境や権力に支配されているように見えても、神の御手が私たちを支えている。
2.外的安心と内的冷え込み
(1)ペテロは「炭火で暖まりながら」否認を重ねた。
(2)快適さや安全を優先すると、信仰の証しを失う危険がある。
3.失敗を通して働く神の恵み
(1)ペテロの三度の否認は、イエスの預言の成就であった。
(2)失敗は恥で終わらず、悔い改めと回復へと導かれる。



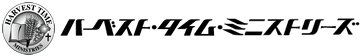
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(08)―24章でたどる神の救済史 7章 「ダビデ契約とメシアの希望」サムエル記第二7章
創造から新天新地へ(07)―24章でたどる神の救済史 6章 「奴隷生活から定住生活へ」ヨシュア記1章
創造から新天新地へ(01)―24章でたどる神の救済史 序章
60分でわかる旧約聖書(28)ホセア書
創造から新天新地へ(06)―24章でたどる神の救済史 5章 「シナイ契約と神の民の召し」出エジプト記20章
創造から新天新地へ(02)―24章でたどる神の救済史 1章 「世界の始まり」創世記1章