私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
2025年 ハーベスト夏期聖会 説教について考える(2)―聞く側の視点から―
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
説教を聞く側に要求される5つの心構え(ABCDE)
ハーベスト夏期聖会
説教について考える(2)
-聞く側の視点から-
はじめに
(1)この説教を語る理由
①新しいスタートを切った自分にとって、説教は最優先課題である。
②良い説教とは
*聖書的(Biblical)
*論理的(Logical)
*実際的(Practical)
③前回は、語る側の視点から、5つのポイント(あいうえお)を紹介した。
④今回は、聞く側の視点から、5つのポイント(ABCDE)を紹介する。
⑤説教について考えるのは、語る側にとっても、聞く側にとっても、重要なこと。
*説教は、語り手、聞き手、聖霊が協力して作り上げる芸術である。
*礼拝の場は、非日常、超日常の世界に変わる。
説教の形態の歴史的変遷
(1)初代教会(1~4世紀)— 即興的で聖書中心の説教
(2)中世(5~15世紀)— ラテン語による典礼中心の説教
①典礼の一部として短い説教が行われた(ミサの中のホミリー)。
(3)宗教改革(16世紀)— 聖書中心の説教の復興
①典礼から講解説教へ(説教が礼拝の中心となる)
②ラテン語から母国語の説教へ(理解可能な説教となる)。
(4)近世(17~18世紀)— 大覚醒運動と感情に訴える説教
①「野外説教」や「クルセード説教」の発展
②感情的・劇的な説教スタイル(聴衆の反応を意識した説教)
(5)近代(19~20世紀)— メディアを活用した説教
①ラジオ・テレビ伝道の登場(説教が広範囲に届くようになる)
②アメリカで「リバイバルクルセード」が流行。
③都市型の大規模教会が増える(メガチャーチの誕生)。
(6)現代(21世紀)— デジタル時代の説教
①インターネットを活用した説教(YouTube・Zoom・SNSで配信)
②短い説教が人気(聞き手の集中力に対応)
③メガチャーチと家の教会の二極化
④デジタル時代のメリット(利点)
*世界中に届く説教(YouTube、Zoom、SNSの活用)
*アーカイブによる学びの継続(何度も学び直せる)
*迫害地域での宣教の拡大(オンラインでアクセス可能)
⑤デジタル時代のデメリット(欠点)
*「ただ聞くだけ」の受動的信仰(礼拝の一体感の喪失)
*エンタメ化・アクセス数重視(心地よい話に偏る危険性)
*異端や偽教師の教えが拡散しやすい環境(識別力が必要)
*「切り取り志向」がもたらす文脈無視の危険性
説教を聞く側に要求される5つの心構え(ABCDE)
Ⅰ.Awe(畏敬)
1.畏怖と畏敬は異なる。
(1)畏怖とは、畏+怖である。
①神の裁きを恐れる感情(アダムは罪を犯して神から隠れた)
(2)畏敬とは、畏+敬である。
①神の偉大さに驚き、敬意を抱く態度(イザヤの場合は、畏怖→畏敬)。
②畏敬は、信仰者の重要な資質である。
③箴9:10
Pro 9:10 【主】を恐れることは知恵の初め、/聖なる方を知ることは悟ることである。
④畏敬の欠如は、今日の礼拝における最大の問題の一つである。
2.畏敬の基となる3つの要素
(1)神の聖さの認識
①イザ6:3
Isa 6:3 互いにこう呼び交わしていた。/「聖なる、聖なる、聖なる、万軍の【主】。/その栄光は全地に満ちる。」
②畏敬は、臨在感と比例する。
(2)神の権威の受容
①説教は、神のみことばの宣言であり、単なる人間の意見ではない。
(3)神の御業への驚き
①ロマ11:33
Rom 11:33 ああ、神の知恵と知識の富は、なんと深いことでしょう。神のさばきはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。
3.畏敬の念を失った人々の例
(1)ナダブとアビフ(レビ10章)
①アロンの息子たちは、異なる火(異なる香り)を主の前に献げた。
②神の火が彼らを焼き尽くした。
(2)ウザ(2サム6章)
①契約の箱は、ケハテ族が棒を使って運ばなければならない。
②ウザ(アビナダブの子)は、契約の箱を牛車で運んだ。
③契約の箱を押さえようと手を伸ばし、打たれて死んだ(畏敬の欠如)。
(3)アナニヤとサッピラ(使5章)
①教会の初期において、献金額を偽った夫婦が即座に死んだ。
②神は、初代教会に対して特に厳格な聖さを求めた。
Ⅱ.Brokenness(砕かれた心)
1.砕かれた心とは
(1)謙遜な心
①詩51:17
Psa 51:17 神へのいけにえは 砕かれた霊。/打たれ 砕かれた心。/神よ あなたはそれを蔑まれません。
2.砕かれた心が必要な理由
(1)神が語られることを素直に受け入れるため
①心が砕かれていない人は、説教を聞いても自分に適用できない。
②心が砕かれていない人は、自分に都合の良い話しか受け入れない。
③「石の心」でなく「柔らかい心」で聞くよう命じられている(エゼ36:26)。
(ILL)「感動を覚える説教を聞いたことがない」と書いてきた人がいる。
(2)聖霊が働きやすくなるため
①砕かれた心の人は、聖霊の示しに素直に応答することができる。
②詩34:18
Psa 34:18 【主】は心の打ち砕かれた者の近くにおられ/霊の砕かれた者を救われる。
(3)悔い改めを可能にするため
①説教の目的は、単に知識を増やすことではなく、霊的な変革をもたらすこと。
②「今日は、どの点で悔い改めるべきか」と問いながら説教を聞くことが重要。
③ヤコ1:22
Jas 1:22 みことばを行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者となってはいけません。
Ⅲ.Calmness(静けさ)
1.内面の静けさは、良い聞き手になるための重要な要素である。
(1)音楽においても、静けさは不可欠な要素である。
①休止府は、音楽の休止を意味しない。
②ピアノがあるから、フォルテが生きる。
③詩46:10
Psa 46:10 「やめよ。知れ。/わたしこそ神。/わたしは国々の間であがめられ/地の上であがめられる。」
2.内面の静けさが必要な理由
(1)神の声を聞くため
①神はしばしば、静寂の中で語られる。
②エリヤは、神の声を「静かなささやき」として聞いた(1列19:11~12)。
(2)聖霊の導きに従うため
①聖霊は、みことばを通して私たちの心に働かれる。
②心が騒いでいる状態では、聖霊の導きを受けるのが難しくなる。
(3)自己吟味をするため(砕かれた心を確認する)
①説教は、自分自身を振り返り、神の前にへりくだる機会である。
(ILL)ガリラヤ湖の湖面
Ⅳ.Discernment(識別力)
1.聖書の警告
(1)聖書は、誤った教えに注意するように繰り返し警告している。
①1ヨハ4:1
1Jn 4:1 愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出て来たので、その霊が神からのものかどうか、吟味しなさい。
2.識別力が必要な理由
(1)すべての説教が真理とは限らないから
①マタ7:15
Mat 7:15 偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、内側は貪欲な狼です。
②注意すべき説教の例
*人間中心の説教
(成功や自己実現を強調し、悔い改めを語らない)
*文脈を無視した説教
(文脈を無視し、部分的な引用で都合の良い解釈をする)
*自己啓発的な説教
(聖霊の働きよりも、人間の努力やポジティブ思考を強調)
(2)私たちは、霊的な戦いの中にいるから
① サタンは、偽りの教えを用いて、信仰を破壊しようとする。
②「少しの間違い」でも、時間が経つにつれて大きな害悪をもたらす。
③1ペテ5:8
1Pe 5:8 身を慎み、目を覚ましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、吼えたける獅子のように、だれかを食い尽くそうと探し回っています。
④疑問があれば、自分で聖書を開き、確認する習慣を養う。
⑤本物に触れ続けていると、偽物を見抜くことができるようになる。
Ⅴ.Examination(自己吟味)
1.デジタル時代の説教の危険性
(1)説教のはしごをし、傲慢になってしまう。
①音楽コンクールの審査員のような感覚で、説教を格付けする。
②識別は必要であるが、格付けは危険である。
(ILL)ゴスペル・コンクールの審査員をしたが音楽を楽しめなかった。
(2)良い説教とは
①神を思い、神と交わる場を提供する説教
②聴衆を自己吟味へと導く説教
2.自己吟味が必要な理由
(1)神の前に正しい態度で立つため
①詩139:23~24
Psa 139:23 神よ 私を探り 私の心を知ってください。/私を調べ 私の思い煩いを知ってください。
Psa 139:24 私のうちに 傷のついた道があるかないかを見て/私をとこしえの道に導いてください。
(2)聖書の真理に照らして、自分の心を探るため
①「あの人に聞かせたい」ではなく、「神は私に何を語っておられるのか」。
(3)罪を告白し、清められるため
①1ヨハ1:9
1Jn 1:9 もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちをすべての不義からきよめてくださいます。
②自己吟味の目的は、「行動を変えること」である。
結論
1.説教に関する3つの真理
(1)説教は、語り手、聞き手、聖霊の3者が共同で作り上げる芸術である。
(2)説教を聞くことは、受動的行為ではなく、能動的行為である。
(3)説教者は、聴衆によって作り上げられる。
2.説教を聞く側に要求される5つの心構え
(1)Awe(畏敬)
(2)Brokenness(砕かれた心)
(3)Calmness(静けさ)
(4)Discernment(識別力)
(5)Examination(自己吟味)



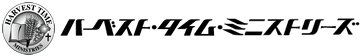
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(13)―24章でたどる神の救済史 12章 「帰還の命令」歴代誌第二36章
創造から新天新地へ(12)―24章でたどる神の救済史 11章 「終末の王国」ダニエル書7章
60分でわかる旧約聖書(26)エゼキエル書
創造から新天新地へ(11)―24章でたどる神の救済史 10章 「新しい契約」エレミヤ書31章
日本人のルーツはユダヤ人か(3)分子人類学から見た日ユ同祖論
Q486 「御名をたたえます」の意味はなんですか。