私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(36)「エルサレム入城」ヨハ12:12~19
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
私たちは、神の御心を理解する者となることができる。
誤解の理由を知ることによって、神の御心を理解する者となることができる。
ヨハネの福音書(36)
「エルサレム入城」
ヨハ12:12~19
1.文脈の確認
(1)前書き(1:1~18)
(2)イエスの公生涯(1:19~12:50)
①公生涯への序曲(1:19~51)
②初期ガリラヤ伝道(2:1~12)
③最初のエルサレム訪問(2:13~3:36)
④サマリア伝道(4:1~42)
⑤ガリラヤ伝道の再開(4:43~54)
⑥2度目のエルサレム訪問(5:1~47)
⑦後期ガリラヤ伝道(6:1~7:9)
⑧3度目のエルサレム訪問(7:10~10:42)
⑨公生涯の締めくくり(11~12章)
*ラザロの復活(第7のしるし)(11:1~44)
*ラザロの復活がもたらした結果(11:45~57)
*マリアによる油注ぎ(12:1~11)
*エルサレム入城(12:12~19)
2.注目すべき点
(1)「時」が満ちた瞬間
(2)公生涯のクライマックスと十字架への道の始まり
(3)人々の期待と神の計画のズレ
(4)弟子たちの無理解
(5)群衆の熱狂と指導者たちの危機感
3.アウトライン
(1)イエスを歓迎する群衆(12~13節)
(2)ろばの子に乗るイエス(14~15節)
(3)無理解な弟子たち(16節)
(4)熱狂する群衆(17~18節)
(5)危機感を抱くパリサイ人たち(19節)
4.結論:今日の信者への適用
私たちは、神の御心を理解する者となることができる。
誤解の理由を知ることによって、神の御心を理解する者となることができる。
Ⅰ.イエスを歓迎する群衆(12~13節)
1.12~13節
Joh 12:12
その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、
Joh 12:13
なつめ椰子の枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。/「ホサナ。/祝福あれ、主の御名によって来られる方に。/イスラエルの王に。」
(1) 「その翌日」
①この日は、棕櫚の聖日と呼ばれる。
②マリアの献身の場面の直後のことである。
③イエスは、ベタニアからエルサレムに向かわれた。
④「勝利の入城」と呼ばれるが、実際は「過越の子羊の選別」である。
(2)祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスを歓迎した。
① 「なつめ椰子の枝を持って」
② 「ホサナ。祝福あれ、主の御名によって来られる方に。イスラエルの王に」
*「ホサナ」とは、「どうか救ってください」という意味である。
*元々は嘆願のことばであるが、ここではメシア到来の歓呼に変わっている。
*詩118:25~26を引用し、イエスを「政治的メシア」として歓迎している。
(3)彼らは、エルサレム入城の意味を誤解していた。
①なつめ椰子の枝を振るのも、祈りのことばも、仮庵の祭りの習慣である。
②「過越の子羊」としてではなく、「政治的メシア」としてイエスを迎えた。
③しかし、仮庵の祭りの前に、過越の祭りが来なければならない。
④初臨のメシアは「受難のしもべ」、再臨のメシアは「神の国の王」である。
⑤イエスは、ろばの子に乗ることによって、その誤解を解こうとした。
⑥しかし、イエスの意図は、その時には理解されなかった。
Ⅱ.ろばの子に乗るイエス(14~15節)
1.14~15節
Joh 12:14
イエスはろばの子を見つけて、それに乗られた。次のように書かれているとおりである。
Joh 12:15
「恐れるな、娘シオン。/見よ、あなたの王が来られる。/ろばの子に乗って。」
(1)イエスの自己宣言
①当時、ろばは平和の象徴であった。
②王は出陣に際して馬に乗ったが、平和な時はろばに乗るのが慣例であった。
③1列1:33で、ソロモンは、ろばに乗って王位を継承した。
1Ki 1:33 王は彼らに言った。「おまえたちの主君の家来たちを連れて、私の子ソロモンを私の雌ろばに乗せ、彼を連れてギホンへ下れ。
④イエスは、自分が「平和をもたらすメシア」であることを宣言した。
(2)メシア預言の成就
①ゼカ9:9の成就
Zec 9:9
娘シオンよ、大いに喜べ。/娘エルサレムよ、喜び叫べ。/見よ、あなたの王があなたのところに来る。/義なる者で、勝利を得、/柔和な者で、ろばに乗って。/雌ろばの子である、ろばに乗って。
②イエスは、この預言が成就するように、意図的に行動した。
③共観福音書では、弟子たちがろばを手配する場面が詳しく描かれている。
④ヨハネは、手続きの詳細を省略している。
⑤ヨハネは、イエスの主権的行動と、預言成就の意義に焦点を合わせている。
(3)イエスの決意
①群衆の期待に応えるのではない。
②神の計画に忠実に歩むことを選ぶ。
③神のしもべは、イエスの献身から教訓を学ぶことができる。
Ⅲ.無理解な弟子たち(16節)
1.16節
Joh 12:16
これらのことは、初め弟子たちには分からなかった。しかし、イエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと、彼らは思い起こした。
(1)イエスの入城時、弟子たちも状況を理解していなかった。
①ヨハネもその中の一人であった。
②ゼカ9:9の預言の成就だと分かったのは、後のことであった。
③ 「イエスが栄光を受けられた後」
*十字架、復活、昇天の出来事の後、聖霊によって理解した。
④ 「それを人々がイエスに行ったのだと、彼らは思い起こした」
*「人々」とは「弟子たち」のことである。
*自分たちもイエスを栄光の王として歓迎したことを思い起こした。
*そのことは、ゼカ9:9の預言と合致していると理解した。
(2)神のご計画は、その時には理解できなくても、後になって分かる。
①分からなくても、疑ってはならない。
Ⅳ.熱狂する群衆(17~18節)
1.17~18節
Joh 12:17
さて、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の中からよみがえらせたときにイエスと一緒にいた群衆は、そのことを証しし続けていた。
Joh 12:18
群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこのしるしを行われたことを聞いたからであった。
(1)ラザロの復活を目撃した群衆
①イエスが行われたしるしを、証しし続けていた。
②つまり、イエスはメシアかもしれないという期待感をばら撒いていたのである。
(2)この証言がエルサレム中に広まり、多くの群衆がイエスを出迎えた。
①彼らの信仰は、「しるし」に惹かれた信仰である。
②イエスが意図している十字架と復活を理解した信仰ではない。
Ⅴ.危機感を抱くパリサイ人たち(19節)
1.19節
Joh 12:19
それで、パリサイ人たちは互いに言った。「見てみなさい。何一つうまくいっていない。見なさい。世はこぞってあの人の後について行ってしまった。」
(1)パリサイ人たちの危機感
①何一つうまくいっていない。
②世はこぞってあの人の後について行ってしまった。
③イエス殺害の陰謀が失敗しかけていると感じた瞬間である。
④パリサイ人たちのことばの中にアイロニー(皮肉)がある。
*イエスは、全世界に救いをもたらすお方である。
結論:今日の信者への適用
1.自分の思い込みを捨てて、聖書に向かう。
(1)群衆は、自分中心の期待でイエスを迎えた。
(2)「政治的メシア」として迎えたが、イエスの真の目的を理解していなかった。
(3)神との「主従関係」が逆転すると、御心が読めなくなる。
(4)神の計画は、常に前進し続けている。
2.聖霊に導かれて、聖書を読む。
(1)弟子たちは、イエスの十字架と復活と昇天後に、聖書を理解した。
(2)これは、聖霊が与えられた結果である。
(3)ヨハネは、かつては分からなかったことが分かるようになったと証言する。
(4)未信者の目には、霊的覆いが掛かっている。
(5)2コリ3:16~17
2Co 3:16 しかし、人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。
2Co 3:17 主は御霊です。そして、主の御霊がおられるところには自由があります。
(6)御霊は、聖書を理解する力と、自由の子として生きる力を与えてくれる。
3.御心が見えなくても、神に信頼し続ける。
(1)神のなさることは、すぐには分からないことが多い。
(2)その場合に必要なのは、忍耐である。
(3)すでに分かっていることに従って従順に歩むべきである。
4.信仰者たちの体験から学ぶ。
(1)ヨセフの生涯(創世記)
(2)モーセの荒野の40年(出エジプト記)
(3)弟子たちとイエスの十字架(福音書)



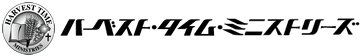
週間アクセスランキング
創造から新天新地へ(13)―24章でたどる神の救済史 12章 「帰還の命令」歴代誌第二36章
創造から新天新地へ(12)―24章でたどる神の救済史 11章 「終末の王国」ダニエル書7章
60分でわかる旧約聖書(26)エゼキエル書
創造から新天新地へ(11)―24章でたどる神の救済史 10章 「新しい契約」エレミヤ書31章
日本人のルーツはユダヤ人か(3)分子人類学から見た日ユ同祖論
Q486 「御名をたたえます」の意味はなんですか。