私たちはプロテスタントのキリスト教福音団体です。『1. 聖書のことばを字義どおりに解釈する 2. 文脈を重視する 3. 当時の人たちが理解した方法で聖書を読む 4. イスラエルと教会を区別する』この4点を大切に、ヘブル的聖書解釈を重視しています。詳しくは私たちの理念をご確認ください。
ヨハネの福音書(34)「ラザロの復活がもたらした結果」ヨハ11:45~57
- このメッセージに感謝を贈る
-
この無料配信メッセージは、皆様の祈りと献金のサポートで成り立っています。
あなたの「ちょっとした感謝」を300円献金で贈ってみませんか?
このメッセージでは...
ラザロの復活は、さまざまな結果をもたらした。
関連キーワード
ヨハネの福音書(34)
「ラザロの復活がもたらした結果」
ヨハ11:45~57
1.文脈の確認
(1)前書き(1:1~18)
(2)イエスの公生涯(1:19~12:50)
①公生涯への序曲(1:19~51)
②初期ガリラヤ伝道(2:1~12)
③最初のエルサレム訪問(2:13~3:36)
④サマリア伝道(4:1~42)
⑤ガリラヤ伝道の再開(4:43~54)
⑥2度目のエルサレム訪問(5:1~47)
⑦後期ガリラヤ伝道(6:1~7:9)
⑧3度目のエルサレム訪問(7:10~10:42)
⑨公生涯の締めくくり(11~12章)
*ラザロの復活(第7のしるし)(11:1~44)
*ラザロの復活がもたらした結果(11:45~57)
2.注目すべき点
(1)「ヨナのしるし」ということば(マタ12:39~40)
Mat 12:39 しかし、イエスは答えられた。「悪い、姦淫の時代はしるしを求めますが、しるしは与えられません。ただし預言者ヨナのしるしは別です。
Mat 12:40 ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるからです。
(2)「ヨナのしるし」は、3つある。
①ラザロの復活
②イエス自身の復活
③2人の証人の復活(黙11章)
3.アウトライン
(1)信じたユダヤ人たち(45節)
(2)パリサイ人に報告したユダヤ人たち(46節)
(3)祭司長とパリサイ人たち(47~48節)
(4)大祭司カヤパ(49~53節)
(5)イエス(54~57節)
4.結論:今日の信者への適用
ラザロの復活は、さまざまな結果をもたらした。
それらの結果を学ぶことで、正しい応答をすることができるようになる。
Ⅰ.信じたユダヤ人たち(45節)
1.45節
Joh 11:45マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くが、イエスを信じた。
(1)イエスの自己啓示は、常に2つの反応を引き起こす。
①信仰と不信仰である。
②イエスは分裂をもたらすために来られたと言える。
(2)ラザロの復活は、メシア的奇跡(ヨナのしるし)である。
①ラザロの復活を目撃した多くの者が、イエスはメシアであると信じた。
②偏見なしにこの「しるし」(証拠)を検証すれば、当然信仰に導かれる。
③幼子のような信仰を神は祝福される。
④深い思索と幼子のような単純な信仰は、両立する。
Ⅱ.パリサイ人に報告したユダヤ人たち(46節)
1.46節
Joh 11:46
しかし、何人かはパリサイ人たちのところに行って、イエスがなさったことを伝えた。
(1)「しかし」は、それとは対照的な反応を示した人々がいたことを示している。
①何人かのユダヤ人たちはエルサレムに戻り、パリサイ人たちに報告した。
②彼らは、ヨナのしるしを目撃しながらも、イエスをメシアと認めなかった。
③彼らは、早く対応策を講じる必要があると判断した。
Ⅲ.祭司長とパリサイ人たち(47~48節)
1.47節
Joh 11:47
祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集して言った。「われわれは何をしているのか。あの者が多くのしるしを行っているというのに。
(1)祭司長とパリサイ人たちは、議会を召集した。
①最高法院とは、サンヘドリンのことである。
②議長、副議長、69人の議員、合計71人。
②急きょ召集したようなので、人数は不足していたと思われる。
(2) 「われわれは何をしているのか」
①なぜこの男の活動を阻止できないのか。
②なぜ行動に移すのが遅いのか。
③この箇所から、役割分担が決まる。
*祭司長たち(サドカイ派)がイエス殺害の主導権を握る。
*パリサイ派がそれを支持する。
(3) 「あの者が多くのしるしを行っているというのに」
①彼らは、イエスが「しるし」を行っていることを認めている。
②その中には、ラザロの復活も含まれる。
③「しるし」を否定しなかった理由がある。
*公に行われている。
*数が多い。
*目撃情報が多い。
2.48節
Joh 11:48
あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやって来て、われわれの土地も国民も取り上げてしまうだろう。」
(1)彼らがこの状況を恐れた理由
①このまま放置すれば、イエスをメシアと信じる人が多く出る。
②彼らは、イエスを王として擁立するだろう。
③そうなると、ローマが介入してくるだろう。
④「土地」(トポス)とは何か。
*狭義の意味は、神殿である。
*広義の意味は、神殿を中心としたユダヤ人の生活空間である。
⑤祭司長たちの優先順位は、職場(神殿)、そして、国民である。
Ⅳ.大祭司カヤパ(49~53節)
1.49~50節
Joh 11:49
しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが、彼らに言った。「あなたがたは何も分かっていない。
Joh 11:50
一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないですむほうが、自分たちにとって得策だということを、考えてもいない。」
(1) 「その年の大祭司であったカヤパ」
①大祭司は生涯その職責に就くというのが、聖書の教えである。
②しかしローマは、大祭司が巨大な権力を握ることを恐れた。
③そのため、都合のよい時に、都合のよい人物を大祭司に任命した。
④カヤパは、紀元18~36年に大祭司であった(18年間)。
⑤彼は、親ローマで、イエスや使徒たちに敵対する勢力の中心にいた。
(2) 「あなたがたは何も分かっていない」
①その通りである。イエスに関する解決策はまだ出されていない。
②これは、軽蔑のことばである。
③これは、ヨハネによるアイロニー(皮肉)でもある。
(3)大祭司カヤパは、解決策を提案した。
①イエスを放置すれば、ローマ軍によって国民全体が滅ぼされることになる。
②一人の人が民に代わって死ねば、国民全体は滅びないので、得策である。
③イエスが人として来られた目的は、まさに「民に代わって死ぬ」ことである。
④カヤパは、イエスが来られた目的を理解しないままで、それを口にしている。
2.51~52節
Joh 11:51
このことは、彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、
Joh 11:52
また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを、預言したのである。
(1)この節は、ヨハネによるアイロニー(皮肉)である。
①カヤパは意図していないが、預言してしまっている。
②大祭司という職責のゆえに、神は彼に預言を与えたのである。
(2) 「散らされている神の子らを一つに集める」
①「散らされている神の子ら」とは、異邦人信者のことである。
②カヤパはユダヤ人のためにと考えていたが、イエスの死は、異邦人をも救う。
③イエスの死は、新しい時代をもたらす。それが教会時代である。
④イエスの死は、人間の悪意による死ではなく、神の愛と計画による死である。
3.53節
Joh 11:53 その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。
(1)第一のヨナのしるしは、神の意図とは異なる結果をもたらした。
①サドカイ人とパリサイ人たちは、第一のヨナのしるしに応答しなかった。
②それどころか、彼らはイエスに対してより敵対的になった。
③イエス殺害の陰謀が、その日から現実化した。
Ⅴ.イエス(54~57節)
1.54節
Joh 11:54
そのために、イエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去って、エフライムという町に入り、弟子たちとともにそこに滞在された。
(1)イエスの時は、まだ来ていない。
①イエスはユダヤを去り、エフライムという町に入られた。
②ベタニヤの北約25kmに位置する町であろう。
③ユダの荒野に近い地方。危険が迫れば逃げることができる。
④次にイエスがユダヤに入るのは、十字架にかかる時である。
2.55~56節
Joh 11:55
さて、ユダヤ人の過越の祭りが近づいた。多くの人々が、身を清めるため、過越の祭りの前に地方からエルサレムに上って来た。
Joh 11:56彼らはイエスを捜し、宮の中に立って互いに話していた。「どう思うか。あの方は祭りに来られないのだろうか。」
(1)多くの人々が、過越の祭りの前にエルサレムに上って来た。
①儀式的に汚れた人は、自らを清める必要があった(民9:6~13)。
②それ以外にも、自発的に清めの儀式を行う人もいた。
③イエスの贖いの死によって「真の清め」が与えられることの伏線になっている。
(2)祭りが始まる前から、人々の関心はイエスに集中していた。
①彼らは、イエスを捜した。
②過越の祭りの中心にいるべきお方が、「指名手配犯」のようになっていた。
③12章に入ると、イエスはエルサレムに登場する。
3.57節
Joh 11:57
祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するように、という命令を出していた。
(1)パリサイ人とサドカイ人が、イエスを捕らえるという一点で共闘している。
①民衆に対する情報提供の要請がなされた。
②イエスに対する敵意が公的政策となった。
③この政策は、死刑を前提とした陰謀である。
(2)情報提供の要請は、ユダの裏切り(13章)の複線になっている。
①イエスを裏切り、逮捕し、法廷に引き渡すことの中に、人の罪の深さを見る。
結論:今日の信者への適用
1.信仰と不信仰は、事実に対する心の態度で決まる。
(1)同じ事実(ラザロの復活)を目撃しながら、人々は二分された。
①信じた人たちvs.パリサイ人のところに行った人たち
(2)信仰の最大の妨げは、道徳的堕落である。
①人は、「信じたくない」から「信じない」のである。
②また、「信じると都合が悪くなる」から「信じない」のである。
③罪人は、心の入り口に「墓石」を置いた状態にいる。
(3)信仰の分水嶺を迎えたとき、正しい選びをしなければ救いから遠ざかる。
①福音を受け入れることは、霊的選択である。
2.神は、人間の陰謀すらも用いる。
(1)カヤパは、民を救うためにイエス殺害の陰謀を提案した。
①彼の発言は、政治的意図から出たものであった。
②彼は自分でも理解しないままで、イエスの死を預言した。
(2)神は、愛のゆえにイエスを十字架につける。
①神は、状況を支配している。
②人間の罪深い動機すらも、神の主権によって計画に取り入れられる。
3.イエスに従うとは、苦難の道を歩むことである。
(1)イエスの居場所を知らせるようとの命令が出されていた(57節)。
①このときイエスは、十字架への道を歩んでいた。
②受難の道は、神の計画に従う道でもあった。
(2)信者は、イエスに従う。
①この福音書の読者たちは、信仰の犠牲を払っていた。
②イエスに従う道は、苦難の道であるが、いのちに至る道でもある。



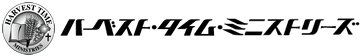
週間アクセスランキング
ヨハネの福音書(42)「父なる神への唯一の道」ヨハ14:1~14
ヨハネの福音書(43)「助け主の約束」ヨハ14:15~31
60分でわかる旧約聖書(4)「民数記」
60分でわかる新約聖書(21)ペテロの手紙第一
ヨハネの福音書(41)「新しい戒め」ヨハ13:31~38
Q455 携挙されないクリスチャンはいますか 。